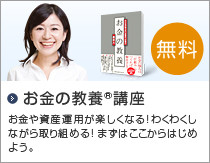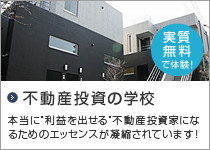投資信託はどう選ぶ?(3)「大きいことは良いことだ」のその後を検証する
人生はわくわくとドキドキで出来ている! サラリーマン上がりの運用相談専門FPやんつです。
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
約6000本という膨大な投資信託の正しい選び方を考えるシリーズ、三回目です。
良い投資信託の条件の一つとして、「資産残高を順調に伸ばしているもの」というのがあります。
ということで、今回は資産残高が大きく、且つ伸ばしているファンドのその後を追跡してみたいと思います。
具体的には投資信託の総合情報サイト「投信資料館」に掲載されている「国内最大ファンドランキング」の上位30銘柄に着眼し、調査することにしました。
まず2010年12月の上位ランク30商品で、2011、2012年と運用資産を伸ばしているものをピックアップし、最近の成績をチェックするという手順です。
ところがビックリ!
2010年から2年連続で資産を増やしているものが、わずか2銘柄しかありません。30本中にです…。
1.フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド …米ドル建て高利回り事業債に投資
2.高金利先進国債券オープン(毎月分配型):月桂樹…「高利回り先進国債券ファンド 」を通じ、ソブリン債や社債、CPなどに投資
2銘柄しかないというのも驚きですが、どちらも債権というのも時代ですね。
2010年といえばリーマンショックの傷もまだ癒えぬ頃。株式市場には資金が流れず、高金利の債権にシフトしていたと考えられます。アベノミクス効果も本格的には2012年から。
ただ高金利債権といえばリスクも高いため敬遠される気もしますが、高利回りという言葉の魔力でしょうか…。
2本だけの追跡ではつまらないので、連続で伸びている訳ではないが組成方針に妥当性がありそうで、その後も期待できるものを独断で4本追加することにしました。
以下の4本です。
3.財産3分法ファンド「不動産・債券・株」(毎月分配型) …国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%に分散投資
4.DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算):ハッピークローバー …高格付資源国の公社債(カナダ、豪、ニュージーランド、ノルウェーなどのAA以上の債権)
5.マイストーリー分配型(年6回)Bコース …世界の債券、国内外の株式を対象とする投資信託証券を通じ、インカムゲイン+キャピタルゲインの獲得を目指す
6.野村世界6資産分散投信(分配コース) …国内および外国の債券、国内および外国の株式、国内および外国のREITにバランスよく投資
この当時は債券系やREITが伸びていた時代の様で、株式型はなく3本がバランス型です。リーマンショックに懲りて安定成長狙いの時代だったのでしょうか。残る資源国の公社債というのも魅力的な気がします。
ベンチマークとしては前回同様、MSCIコクサイに連動する、ニッセイ外国株式インデックスファンドをチョイス。
選定した6本のその後(2017~2019年の3年間の成績)をベンチマークと比較することにしました。分配金込価格と純資産残高の3年間での増減率の比較です。
(その後驚異的な伸びをみせ、今では残高5000億を超す「ひふみ投信」は当時はまだランクインしてませんでした)
■ 運用資産残高上位 追跡調査

選定した6本全て分配金型(毎月、隔月)というのはやはり時代でしょうか。
分配型は複利効果も無く、税効率も悪いのでお得とは言えないのですが、今も昔も高齢者には人気があります。
定期的に分配がもらえるのが嬉しいという心理は理解できますが、普通分配と特別分配の違い等は分かっているんでしょうか? メリット、デメリットを理解して買っているならいいんですが…。
さて、分配金込価格と純資産残高の増減率をみてみましょう。
分配金込み価格はなんとか5本がプラスですが、なんとも上昇幅が少ない。+10%越えはフィデリティ・USハイ・イールドと財産3分法の2本だけです。
ベンチマークが3年で約36%上昇していることと考えると物足りない限り。
純資産残高に至っては殆どが3年間で減少です。
唯一、財産3分法ファンドだけが2指標共にプラスです。ただバランス型だけに大きなリターンは望みにくい理屈はありそうですが、ベンチマークとの見劣り感は否めません。
国内最大ファンドランキングの上位といえば、過去に大いに売れた商品でもあります。
必ずしも長期的にインデックスに勝るとは限らない商品が、何千億もの残高というのは、売る側の力なんでしょうか、それとも買う側の勉強不足か…。
運用残高が大きいからと言って、何時までも好調という訳ではない。
その時代の人気によって商品が選ばれているのが実態。
これが今回の結論のようです。
アクティブファンドの選び方に何か蓋然性のある手法は無いか? と始めた本シリーズですが、アクティブファンドの良さがなかなか見えてきません。
毎回「インデックスが最強説」を裏付ける結果になっています。
もう少し、なにかいい購入尺度はないか考えてみます。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。
※本記事は特定の商品を推奨、あるいは誹謗中傷するものではなく、あくまで個人的な見解に基づく記事です。