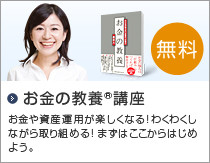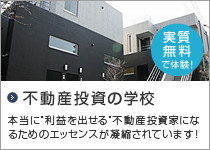相続税対策 実践録(1) 節税対策の基本
こんにちは!53歳からあわててお金の勉強中の、不動産投資家やんつです。
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
今回も相続税のお話です。

前回、相続税対策の前に話し合いのできる土台を作ってください、
とお願いしました。
これが出来ればいよいよ相続対策の4ステップです。
1)争続対策(分割協議)
2)節税対策(相続税対策)
3)納税資金対策
4)各種継承・事後管理
とまぁ、偉そうに言ってますが、
わたしもきちんと順序良く出来た訳ではありません。
2006年に父が75歳で亡くなりましたが、
存命中は財産の話について相談したこともありませんでした。(´Д` )
相続手続きを進める中で、資産と負債を洗い出す必要があり、その時に初めて財産の確認をしました。
相続人は母と兄とわたし(次男)の3人です。
母がいますので、法廷相続分としても1/2は権利があります。
わたし達兄弟もすでに生活基盤があり、そんなに多く相続したい希望がある訳でもなく、
分割については特に揉めることもありませんでした。
相続財産のかなりの部分が田であり、
もらってもあまり意味はない(稲作はほとんど収益にならない)、ということも大きかったのかもしれません。
相続税も配偶者控除が大きいのであまり税金は掛かりませんでした。
ただ、この時に始めて相続というものを知ったのです。
なんだか相続って面倒くさい・・・
ちゃんと準備した方がいいかも・・・
念のため、母が亡くなった時の試算をしてみました。
(残る配偶者の死亡による相続、これを2次相続といいます)
計算してみてビックリ!
父の相続の時には、既に母名義になっていたため対象外だった実家の家屋敷が
今度は対象となるためかなりの金額になりそうです。
えーーーーっ! こんなに税金かかんの!?
サラリーマンじゃぁ払えんがね・・・
こういうと、ずいぶん資産家で贅沢な悩みのようですが・・・
相続財産のほとんどが田や実家などの収益を生まない資産です。
キャッシュフローを生まない不動産は資産とは言えません!
むしろ、持っているだけで固定資産税はかかる・・・
このままでは資産家どころか死惨家になってしまう!
なんとかしなくては!
と、慌てふためいて勉強を始めたという次第です・・・(>_
あなたにはこんな泥縄にならないようにして欲しいと思います。 m(__)m
一般的に相続税対策といえば4ステップのうち
2)~3)の部分を言います。
対策は大きく4つに分かれ、その戦術はこんな感じです。
①【贈与の活用】
・住宅取得等資金の贈与
・教育資金の一括贈与
・相続時精算課税制度
・暦年贈与
②【評価額の圧縮】
・生命保険
・借金
・貸家建付け地(アパート)
・小規模宅地の特例
③【法人の活用】
④【養子の活用】
③は富裕層向けで、「相続時に活用する」というより事前に資産管理会社を作って(法人成り)、所有を分散します。
自営業、経営者の方向けです。
一般向けではないのでここでは説明は省きます。
④は、子の配偶者や孫を養子にしてしまうという荒業です。
相続人を増やすとともに相続税の発生回数を減らす効果があります。
(祖父→子→孫 の2回を 祖父→子+孫(養子)の1回に)
相続税のために養子縁組をするなんて!、と思いますが
実は一世代前には意外とよく使われた手法のようです。
家督を守り、相続していく意識が強かったんだと思います。
子だくさんの時代で子供の権利なんて考えもしなかったんでしょう。
今でも、事情によっては強力な手法になるかもしれませんが・・・
③、④はやや特殊なので、主たる戦略としては①、②になります。
色んな手段がありますが、ちょっとお薦めは「相続時精算課税制度」です。
その理由と注意点は次回・・・
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
今回も相続税のお話です。

前回、相続税対策の前に話し合いのできる土台を作ってください、
とお願いしました。
これが出来ればいよいよ相続対策の4ステップです。
1)争続対策(分割協議)
2)節税対策(相続税対策)
3)納税資金対策
4)各種継承・事後管理
とまぁ、偉そうに言ってますが、
わたしもきちんと順序良く出来た訳ではありません。
2006年に父が75歳で亡くなりましたが、
存命中は財産の話について相談したこともありませんでした。(´Д` )
相続手続きを進める中で、資産と負債を洗い出す必要があり、その時に初めて財産の確認をしました。
相続人は母と兄とわたし(次男)の3人です。
母がいますので、法廷相続分としても1/2は権利があります。
わたし達兄弟もすでに生活基盤があり、そんなに多く相続したい希望がある訳でもなく、
分割については特に揉めることもありませんでした。
相続財産のかなりの部分が田であり、
もらってもあまり意味はない(稲作はほとんど収益にならない)、ということも大きかったのかもしれません。
相続税も配偶者控除が大きいのであまり税金は掛かりませんでした。
ただ、この時に始めて相続というものを知ったのです。
なんだか相続って面倒くさい・・・
ちゃんと準備した方がいいかも・・・
念のため、母が亡くなった時の試算をしてみました。
(残る配偶者の死亡による相続、これを2次相続といいます)
計算してみてビックリ!
父の相続の時には、既に母名義になっていたため対象外だった実家の家屋敷が
今度は対象となるためかなりの金額になりそうです。
えーーーーっ! こんなに税金かかんの!?
サラリーマンじゃぁ払えんがね・・・
こういうと、ずいぶん資産家で贅沢な悩みのようですが・・・
相続財産のほとんどが田や実家などの収益を生まない資産です。
キャッシュフローを生まない不動産は資産とは言えません!
むしろ、持っているだけで固定資産税はかかる・・・
このままでは資産家どころか死惨家になってしまう!
なんとかしなくては!
と、慌てふためいて勉強を始めたという次第です・・・(>_
あなたにはこんな泥縄にならないようにして欲しいと思います。 m(__)m
一般的に相続税対策といえば4ステップのうち
2)~3)の部分を言います。
対策は大きく4つに分かれ、その戦術はこんな感じです。
①【贈与の活用】
・住宅取得等資金の贈与
・教育資金の一括贈与
・相続時精算課税制度
・暦年贈与
②【評価額の圧縮】
・生命保険
・借金
・貸家建付け地(アパート)
・小規模宅地の特例
③【法人の活用】
④【養子の活用】
③は富裕層向けで、「相続時に活用する」というより事前に資産管理会社を作って(法人成り)、所有を分散します。
自営業、経営者の方向けです。
一般向けではないのでここでは説明は省きます。
④は、子の配偶者や孫を養子にしてしまうという荒業です。
相続人を増やすとともに相続税の発生回数を減らす効果があります。
(祖父→子→孫 の2回を 祖父→子+孫(養子)の1回に)
相続税のために養子縁組をするなんて!、と思いますが
実は一世代前には意外とよく使われた手法のようです。
家督を守り、相続していく意識が強かったんだと思います。
子だくさんの時代で子供の権利なんて考えもしなかったんでしょう。
今でも、事情によっては強力な手法になるかもしれませんが・・・
③、④はやや特殊なので、主たる戦略としては①、②になります。
色んな手段がありますが、ちょっとお薦めは「相続時精算課税制度」です。
その理由と注意点は次回・・・