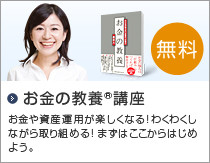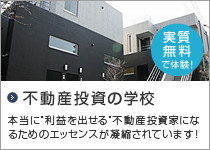相続税対策 実践録(2) 節税対策の基本
こんにちは!53歳からあわててお金の勉強中の、不動産投資家やんつです。
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
今回も相続税のお話です。
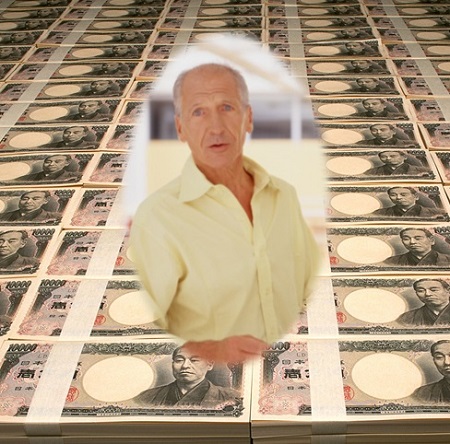
前回お話ししたように相続税対策といえば
まず①贈与の活用テクニックがあります。
①【贈与の活用】
・住宅取得等資金の贈与
・教育資金の一括贈与
・相続時精算課税制度
・暦年贈与】
この中で、あまり知られていないけど知っておいたほうがいいのが
「相続時精算課税制度」です。
生前贈与を円滑化するため2003年に導入されました。
高齢者から若年層への資産の早期移転と活用を目的としたもので、
65歳以上の直系尊属(両親)より20歳以上の直系卑属(子、孫)への1人当たり2,500万円までの贈与に関し贈与税を繰り延べするものです。
税金が掛からない訳ではなく、相続時に清算します。
わたしもこれを活用しました。
父親が入退院を繰り返していた晩年、
やっとローンを払い終えた築古アパートがありました。
築古のため客付も苦戦しており、母は持て余し思い余って処分したいと相談してきました。
管理会社と話したところ、リフォームすれば運営可能との意見。
そこでわたしが管理を引き受けることにしました。
ところが所有権は父のままです。
何をするにも入院中の父にサインをもらう必要があります。
これでは面倒なばかりです。
そんな時に銀行に勤めていた友人が、
「相続時精算課税制度というのがあるよ~」
と教えてくれました。
これで贈与税を払わず資産活用が出来る!
収益が上がれば、それをプールして納税資金の備えにも出来る!
こうして資産活用のスタートを切ることができました。
(と言っても、本格的に勉強し出すのは2010年からですが・・・)
「相続時精算課税制度」のメリットです。
・相続財産を早めに活用できる
→何といってもこれが大きいですね。資産運用の自由度とスピードが違います。
利回りを生みだす事ができればその収益を享受でき、その差はとても大きなものになります。
・贈与時の評価額で固定できる。
→これは資産が贈与後値上がりした場合にお得です。
精算は相続時ですが、評価額の計算は贈与時が基準となります。
評価額が低いうちに適用できれば評価額が上がってもへっちゃらです。
まぁこれは、土地神話が崩壊した今はあまり該当しないかもしれません。
今は相続時に下がっていることの方が多いかも・・・
・適用枠が大きい
→2,500万円が上限であり、かなり使い出があります。
上限を超えても超えた部分に20%の贈与税を納税することで利用可能です。
納税分も相続時に再度清算されます。
良いことだらけではなく、注意点もあります。
・贈与税としての節税効果がない
→110万円の基礎控除がないためその効果を享受できません。
全て相続時に計算対象となります。逆に相続税の控除額対象にはなります。
・二度と通常の贈与税に戻れない
→いったん選択すると、普通の贈与が出来なくなります。
今後も相続税の増税が想定される場合は、その回避策にはなりませんね。
・制度が複雑、手続きが煩雑
→配偶者は適用対象外です。子に関しては20歳以上の子。
孫に関しては既に子が亡くなっている場合に限ります(当時。2015年からは緩和)
また「相続時精算課税制度選択の届け出」が必要です。
後で相続放棄をしても、本制度適用部分は除外されます。
結果、この制度を適用した場合としなかった場合の損得計算が大変です。
どちらが得か判断が難しいです。
今年は適用条件が緩和されましたが、
どちらかというと傾向は、贈与税の減税と相続税増税がトレンドです。
使わない方がお得というケースが増えてくるかもしれません。
将来は相続税と贈与税が統合化される可能性もあります。
相続税を止めて資産税にシフトという議論もあります。
活用の場面は少し減るのかもしれませんが………
まぁ覚えておいて損はないと思いますよ。
次回は生命保険の活用です。
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
今回も相続税のお話です。
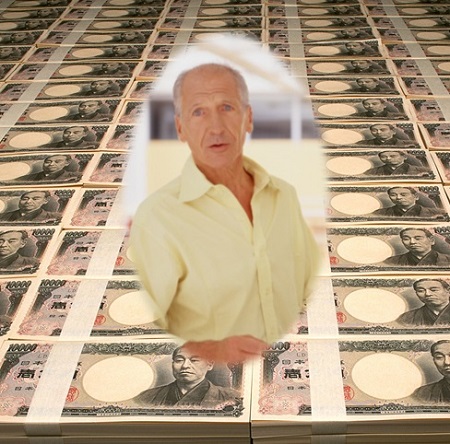
前回お話ししたように相続税対策といえば
まず①贈与の活用テクニックがあります。
①【贈与の活用】
・住宅取得等資金の贈与
・教育資金の一括贈与
・相続時精算課税制度
・暦年贈与】
この中で、あまり知られていないけど知っておいたほうがいいのが
「相続時精算課税制度」です。
生前贈与を円滑化するため2003年に導入されました。
高齢者から若年層への資産の早期移転と活用を目的としたもので、
65歳以上の直系尊属(両親)より20歳以上の直系卑属(子、孫)への1人当たり2,500万円までの贈与に関し贈与税を繰り延べするものです。
税金が掛からない訳ではなく、相続時に清算します。
わたしもこれを活用しました。
父親が入退院を繰り返していた晩年、
やっとローンを払い終えた築古アパートがありました。
築古のため客付も苦戦しており、母は持て余し思い余って処分したいと相談してきました。
管理会社と話したところ、リフォームすれば運営可能との意見。
そこでわたしが管理を引き受けることにしました。
ところが所有権は父のままです。
何をするにも入院中の父にサインをもらう必要があります。
これでは面倒なばかりです。
そんな時に銀行に勤めていた友人が、
「相続時精算課税制度というのがあるよ~」
と教えてくれました。
これで贈与税を払わず資産活用が出来る!
収益が上がれば、それをプールして納税資金の備えにも出来る!
こうして資産活用のスタートを切ることができました。
(と言っても、本格的に勉強し出すのは2010年からですが・・・)
「相続時精算課税制度」のメリットです。
・相続財産を早めに活用できる
→何といってもこれが大きいですね。資産運用の自由度とスピードが違います。
利回りを生みだす事ができればその収益を享受でき、その差はとても大きなものになります。
・贈与時の評価額で固定できる。
→これは資産が贈与後値上がりした場合にお得です。
精算は相続時ですが、評価額の計算は贈与時が基準となります。
評価額が低いうちに適用できれば評価額が上がってもへっちゃらです。
まぁこれは、土地神話が崩壊した今はあまり該当しないかもしれません。
今は相続時に下がっていることの方が多いかも・・・
・適用枠が大きい
→2,500万円が上限であり、かなり使い出があります。
上限を超えても超えた部分に20%の贈与税を納税することで利用可能です。
納税分も相続時に再度清算されます。
良いことだらけではなく、注意点もあります。
・贈与税としての節税効果がない
→110万円の基礎控除がないためその効果を享受できません。
全て相続時に計算対象となります。逆に相続税の控除額対象にはなります。
・二度と通常の贈与税に戻れない
→いったん選択すると、普通の贈与が出来なくなります。
今後も相続税の増税が想定される場合は、その回避策にはなりませんね。
・制度が複雑、手続きが煩雑
→配偶者は適用対象外です。子に関しては20歳以上の子。
孫に関しては既に子が亡くなっている場合に限ります(当時。2015年からは緩和)
また「相続時精算課税制度選択の届け出」が必要です。
後で相続放棄をしても、本制度適用部分は除外されます。
結果、この制度を適用した場合としなかった場合の損得計算が大変です。
どちらが得か判断が難しいです。
今年は適用条件が緩和されましたが、
どちらかというと傾向は、贈与税の減税と相続税増税がトレンドです。
使わない方がお得というケースが増えてくるかもしれません。
将来は相続税と贈与税が統合化される可能性もあります。
相続税を止めて資産税にシフトという議論もあります。
活用の場面は少し減るのかもしれませんが………
まぁ覚えておいて損はないと思いますよ。
次回は生命保険の活用です。